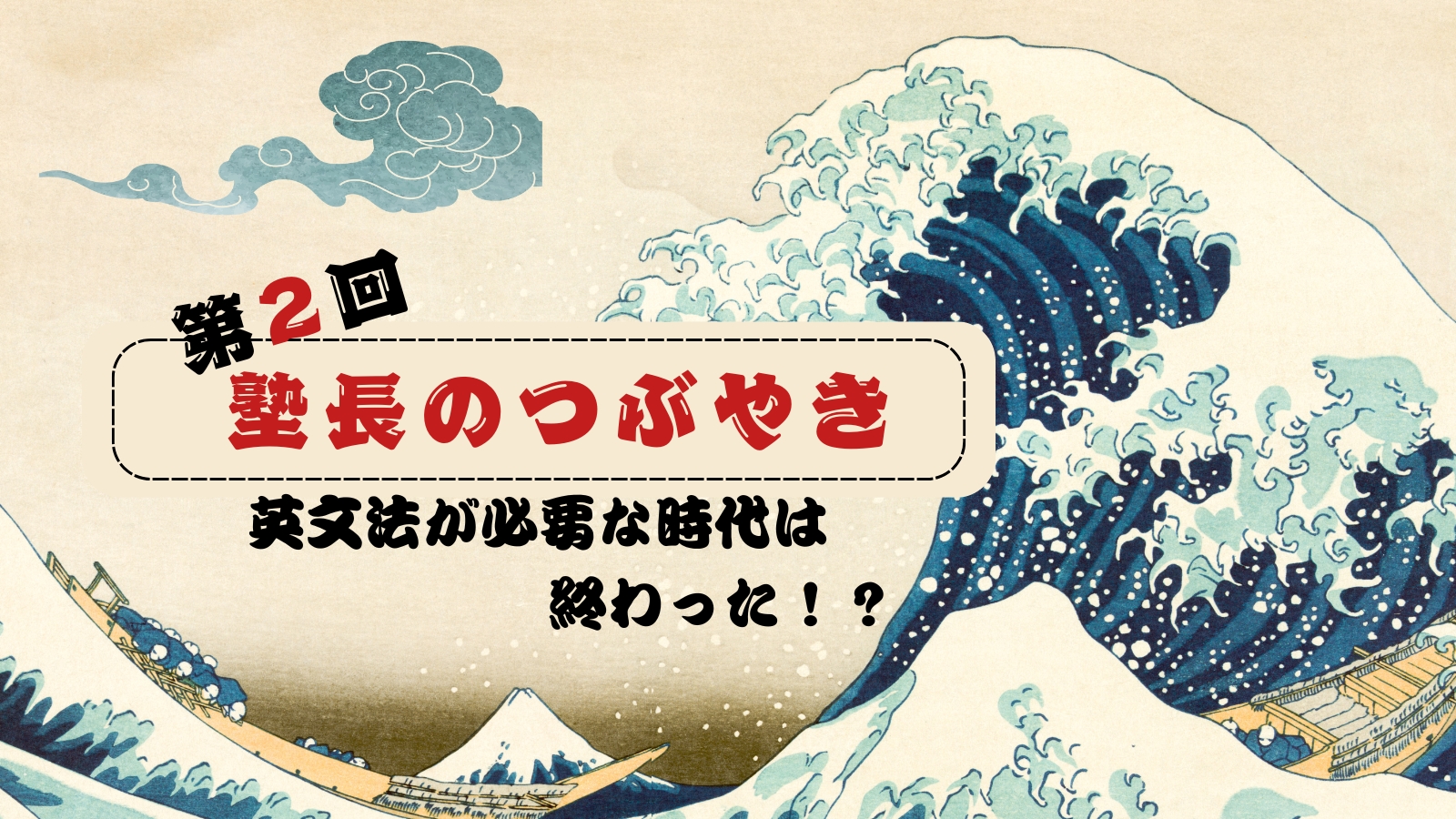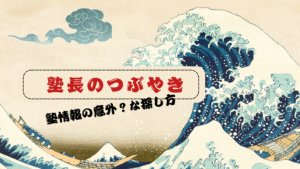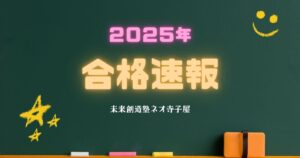年々減りつつある単体知識型英文法問題
みなさんこんにちは、未来創造塾ネオ寺子屋塾長の宮坂です。当塾は特に英語と現代文の指導を得意としていますが、今日はその指導経験の中から英文法の現状について取り上げてみようと思います。
昨今、英語における文法問題の出題が各種試験で減少しつつあります。個人的な印象では大学入試ベースでこの流れを決定付けたのは、大学入試センター試験に代わって2021年1月から施行された大学入学共通テストではないかと思います。センター試験時代には大問2に必ず「4択型文法・語法・イディオム問題」と「語句の並び替え問題」が出題されており、これらを解くためには文法分野単体に関する詳細な知識が必要不可欠でした。これに対して大学入学共通テストでは、いわゆる文法知識単体のみを問う設問が消滅し、全体として相当な量の英文を時間内に読みこなさなければいけない「速読力と事務処理能力重視」の出題に変わってきています。この流れの根底には文科省が掲げる英語教育理念の変化と学習指導要領の改訂があり、国公私立大学入試でも共通テスト同様に文法知識単体を問う問題の減少が目立つようになってきました。
また、高校・大学受験生にはお馴染みの実用英語技能検定(いわゆる英検)でも、特に準2級以上の級において大学入学共通テストの傾向と同様に単純知識問題としての文法問題が大幅に削減されてきています。英検は民間機関の実施する検定試験ですから文科省や学習指導要領の方針変更の直接的な影響は受けない建前ですが、学校教育や入試で活用されている現状を考えると大なり小なり影響を受けるのは道理と言えます。
これらの傾向を踏まえて、英文法の勉強に時間をかけることへ疑問を抱く声が聞かれるようになってきました。英文法の勉強は必要最低限でいい、とにかく長文をたくさん読むことが必要であると。英語試験全体の中で英文法の重要性は相対的に下がってきていると。確かに各種試験において文法問題単体の出題は間違いなく少なくなってきています。では本当に英文法の勉強は必要最小限度に留めてよいのでしょうか。
そもそも英文法とはどういうものなのか
この問題を考えるにあたり、まず英文法というものが何のために役立つのか考えてみましょう。言葉というものは相手に自分の意図を伝えるために使われるものである以上、誰が聞いて(見て)も同じ意味に理解出来るように一定の形を守る必要があります。その一定の形に言葉を正しく組み立てて使うための「決まり」や「仕組み」の体系を文法と言います。つまり英文法とは英語という言語を正しく組み立てるためのルールであると言うことが出来ます。
私たち日本人は通常日本語を母語として育ってきているはずなので、言葉を考える時には頭の中で無意識の内に日本語のルールを思い浮かべていることになります。ところがご存知のとおり日本語と英語の文法には大きな違いがあります。これが日本語話者が英語を苦手とする決定的な理由の一つであり、英語を正しく理解するためには英文法の勉強が必要であると言われてきた所以です。
全体の雰囲気から「なんとなく」の意味だけを把握するなら単語の意味を適当につなげるだけでどうにかなる場合もありますが、文章や相手の意図を正確に理解したいという場合はやはり日本語と英語の文法の違いをしっかりと意識しながら読む・聞く必要があります。これが読む・聞くではなくて自分の意図を書く・相手に伝えるとなるとなおさら英語の組み立てのルールを知らなければなりません。
果たして試験における英文法の重要性は下がってきているのか
英語を理解するためには文法はどうやら重要であることは分かった、それでも試験では英文法問題は減ってきている…ならばやはりそこまで文法に力を入れる必要性はないのでは?少なくとも試験における文法の重要性は下がってきているのではないか?と考える方もいるかもしれません。しかしこれについては塾講師としての17年の経験も踏まえて断固としてノー!と答えます。たとえば次の英文を訳してみて下さい。
単語の意味だけを繋いでなんとなくで読んでいる人はこれを「私はその問題について考えることをやめた」と訳してしまいます。実はこれは大変に多い誤答で、正解は「私はその問題について考えるために立ち止まった」となります。stop to think自体は口語表現としてもよく使われるものなので、知ってさえいれば解けると言えなくはないですが、逆に言えば知らなければ感覚頼みで正反対の意味で捉えてしまうということなのです。このような誤った解釈を防いでくれるのがまさに文法力だと言えます。
いかがですか、この解説が何を言っているか分かりましたでしょうか。もちろん授業では箇条書きではなく筋道立てて講義しますが、直接に文法知識が問われる問題が少なくなったとしても英文の正確な意味を理解するためにはこのように細かい文法知識が必須なのです。大学入学共通テストのような読解中心の出題であったとしても、英文の意味を正反対にとらえてしまったら大惨事になってしまうことは言うまでもないでしょう。また各種試験の解説などを読むと分かりますが、長文・対話文の説明にも文法の用語や考え方が山ほど登場します。英文法を知らないとそもそも解説の意味すら分からず復習がままならないということになりかねません。
長文を読んで様々な表現に慣れていることはもちろん重要です。しかしその上で知らないことがあっても英文を正しく解釈するための最後の砦、それが英文法なのです。
※解説の意味がよくわからなかった高校2年生以上の方は文法テキスト等で「自動詞・他動詞」「不定詞」「動名詞」の単元をしっかり復習しておいて下さい。当塾の塾生さんであればいつでも解説します。
結論 結局英文法の時代は・・・
以上からお分かりの通り、結論として英文法の重要性は全く変わっていません。それどころか増してきていると言っても良いくらいです。というのも各種試験で英文法の単純知識問題が減少した代わりに、英検や大学入試(一部の私立一般入試や国公立2次試験)ではライティング問題の出題が増加してきているからです。前述した通り英文法とは英語という言語を正しく組み立てるためのルールであるため、それを知らない状態では正しい英文など書けるはずがありません。ですから見かけ上では英文法の問題が減ったように見えても実際には増えている、それくらいの意識で英文法の勉強に取り組むべきです。単純知識の問題こそ減りましたが逆に活きた英文法の使い方、まさに活用の仕方に焦点が移ったということです。英文法の時代は終わったのではなく新時代を迎えているのです。
今後はどうしてその訳になるのか分からない、そういった英文があったらぜひ学校の先生やお通いの塾の講師に質問してみましょう。もしその際に「たくさん読んでいくうちに慣れるから」や「そういうものだと思って覚えておいて」などとヘラヘラ答えてくる先生・講師がいたら大体ウンコです。英文法を軽視しているか、説明できるほど自分が理解していないことからの逃げでしかありません。その先生や講師を信頼してついていって良いかどうかのリトマス試験紙としても英文法は機能すると考えておいて良いと思います。